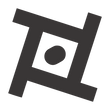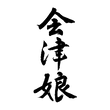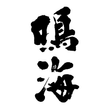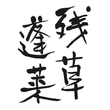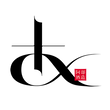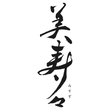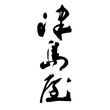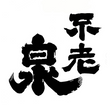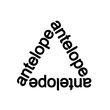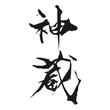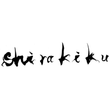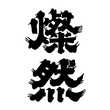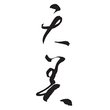2024年末にユネスコ無形文化遺産に登録された日本の「伝統的酒造り」。近年、海外で日本食の人気が高まり、日本への外国人観光客も増加していますが、さらなる日本酒の消費や輸出の増加が期待されています。
今回の酒蔵だよりでは、輸出にも力を入れている京都府 松井酒造蔵元である十五代目 松井治右衛門さんが、肌で感じた変化の兆しについて綴ってくれました。
集まる世界からの視線

2024年12月5日にパラグアイで開かれたユネスコ無形文化遺産保護条約 第19回政府間委員会において、「伝統的酒造り」がユネスコ無形文化遺産に登録されました。伝統的酒造りとは、杜氏・蔵人等がこうじ菌を用い、長年の経験に基づき築き上げてきた酒造り技術のことをいいます。
伝統的酒造りとして、日本酒の製造工程がユネスコの無形文化遺産に登録されたことには大きな意味があります。これまでも海外の方から興味を示していただく機会は比較的多かったのですが、ここにきて日本酒に対する世界的な意識の高まりを実感しています。
実際、12月の登録以降、海外からの問い合わせの数は大きく増加しています。今年は2月までに3か国(フランス・シンガポール・カンボジア)に赴き、日本酒に関心を寄せる皆様と交流を深めることができました。また、例年2月は観光が一休みする時期なのですが、今年はインバウンドのお客様が高止まりしているように感じます。当社のテイスティングルームに来られる海外のお客様も日本酒に大きな興味を示してくださっており、以前よりも日本酒の勉強をしたいという方は確実に増えていて、スタッフが質問攻めにあっている光景を日常的に目にしています。
求められる本場「日本」

フランス出張の際、フランス第二の都市リヨンでの展示会では、わざわざ日本ブースの私たちのところに経済観光担当大臣が来てくれました。これも日本酒が無形文化遺産に登録され、関心を寄せられているからではないかと思っています。
また、特に印象的だったのは、レストランのシェフの皆様と話をしたときのことです。
彼らは常に料理に対して真摯で、自分たちの文化に誇りを持っています。日本の方もそうですが、料理人の皆さんは本当に勉強熱心です。これまでにない新しい技術を生み出すために異なる文化の勉強を欠かしません。
和食の技術や精神性はフレンチのシェフにとって、とても魅力的に映っているように感じました。そして、和の酒である日本酒についても一層、学ぶ意欲を持っています。原料や製造法にとどまらず、「日本ではどんなペアリングをしているのか」、「蔵の持っているストーリーは?」など鋭い質問をされ、彼らはこちらが想像しているよりはるかに、日本酒についてだけでなく、日本そのものについても知りたいのだと感じました。
今回の無形文化遺産登録により、日本酒に対する海外からの関心は今後さらに高まることが予想されます。必要とされる場所で飲んでいただけることがメーカーにとっての幸せですので、引き続き海外輸出にも力を入れていきたいと考えています。
酒造りの幹と枝葉

今回の登録では酒屋万流と言われるほど多彩な酒造りの技に対して、どのように評価をするのか関心を持っていました。あまりに細かく「日本酒はこうあらねばならない!」というような定義付けをしてしまうと、より良い酒造りに対するイノベーションが生まれなくなってしまいかねません。
日本酒に関しては、原料である米を蒸し、麹を育て、もろみを発酵させる(並行複発酵)という基本を押さえていることが重視されています。これはいわば酒造りの骨格と言える部分です。今回の登録内容は、どれほど製造技術の近代化が進んだとしても、ここだけは変わらないという部分を抽出し、それを核心的技術として保護しようとするものでした。
登録決定に至るまで、関係各位の多大なるご尽力があったとを想像しています。世界中で日本酒を楽しんでいただけるようにするために、この機会を有効に活用しなければなりません。松井酒造は、核心的技術という太い幹をしっかりと保持しながら自由に枝葉を伸ばし、色鮮やかな花や実を結ぶようになりたいと思っています。
【酒蔵だより:松井酒造】
- 2023年8月:「中学生の職業体験を受け入れて」
- 2023年10月:「京都から世界へ。観光都市の酒蔵として思うこと」
- 2023年11月:「ゲームやアニメと日本酒のコラボ可能性」
- 2024年1月:「ジン&ラム参入で、日本酒とシナジーを生み出す」
- 2024年3月:「『これからの1000年を紡ぐ企業』として、酒造りの伝統と未来を考える
- 2024年8月:「年30回参加!日本酒イベントの醍醐味とは」
- 2024年11月:「海外出張でみえた日本酒の現在」
- 2025年1月:「「神蔵」のデザインに込めた想いと工夫」
- 2025年4月:「無形文化財登録後に見えた意識の変化」