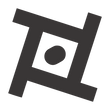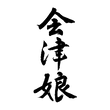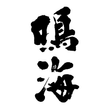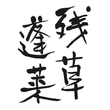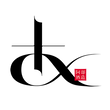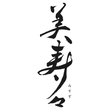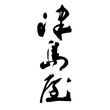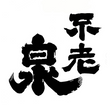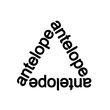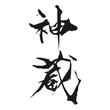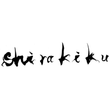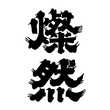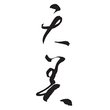生産量の9割は地元で消費されるという北海道・釧路の地酒「福司」。酒蔵がある釧路という街は、札幌や小樽などの西側とは異なる魅力にあふれています。
今回の酒蔵だよりでは、釧路という街の自然、食文化、そして福司との関係性について、通称「醸し屋」こと製造部部長の梁瀬一真さんに綴っていただきました。
"遊びの上級者"が選ぶ、北海道の東側へようこそ
観光の定番は“左側”ルート
北海道に行こう!と思い立ったとき、多くの人が思い浮かべる景色や観光地といえば、札幌・小樽・富良野・旭川あたりではないでしょうか?それらを地図上に点で打つと、どれも北海道の中央から西側に位置します。アクセス面でも、千歳空港を起点とする旅行が一般的で、そこから電車で札幌へ向かったり、レンタカーで各地をめぐったりというプランが多いでしょう。
知る人ぞ知る、“右側”の北海道

釧路の風景
私たちの蔵があるのは、そんな北海道の「右側」、道民の間では「道東(どうとう)」と呼ばれる地域。千歳空港から車で約3時間、東京から名古屋くらいの距離感です。
北海道の東側の風景がすぐに思い浮かぶ人は、相当な北海道好きかもしれません。それくらい、はっきりとした目的がなければなかなか訪れないエリアです。札幌や旭川のような華やかさはなく、観光ガイドの誌面でもやや地味(?)な印象を受けるかもしれません。そんな道東に、ひっそりと広がる街が釧路です。
前回の酒蔵だよりにも書きましたが、釧路の冬は雪が少なく、地面が凍って氷の世界になります。でも実は、とても住みやすい街なのです。雪かきの必要がほとんどないのは、冬の暮らしでは大きなポイント。食べ物もおいしく、初夏には霧が立ち込めて幻想的な街並みに。夏はとても涼しく、近年では「笑えるほど涼しい街」として避暑地のPRもされています。
「何もないけど、全部ある」
「何もない」と言われることもありますが、それは都会と比べて利便性や派手さを基準にしたときの話。プライベートでも離島めぐりが好きな醸し屋の私にとっては、「何もないけど、全部ある」場所だと思っています。
野生動物がすぐそばにいて、カヌーで静かな川を下り、渓流では魚が跳ねる。「のろっこ号」というローカル線が湿原を抜け、空にはタンチョウが舞う……。離島に行くように、“知っている人だけが知っている”旅先。それが釧路です。都会の方にとっては非日常に感じるような景色や体験が、私たちにとっては日常の一部なのです。

蔵のみんなと渓流釣りに行きました
先日も、私は山菜採りに行ってきました。自生しているクレソンやワサビが瑞々しく育っていて、春の恵みを存分に味わいました。以前は蔵のみんなで行者ニンニクを採りに行ったり、渓流釣りをしたりしたことも。山や海の恵みを、自分たちが造った酒で味わうひとときは、やっぱり格別です。
釧路の食は、福司とともにある

釧路グルメ・スパカツ
道東、釧路は気候や自然、観光地としての特色もありますが、“食文化”の面でも独自の進化を遂げています。本州(道外のことを、道民はこう呼びます)ほどの人口や歴史はないかもしれませんが、釧路には釧路の“当たり前”があります。
たとえば──
- ・熱々鉄板にスパゲティ+カツの「スパカツ」
- ・緑色のそば(クロレラ入り)
- ・蕎麦がない“かしわ抜き”(汁だけ!)
- ・北海道“第4のラーメン”、あっさり細縮れ麺の「釧路ラーメン」
どれも道外ではほとんど知られていないですが、地元の人が当たり前に楽しんでいるソウルフードなのです。
そして、これらローカル食文化と深く結びついているのが、地元の酒「福司(ふくつかさ)」です。観光客向けの派手な味ではなく、地元の食卓に根付いた、日常に寄り添う酒。だからこそ、釧路の味にもっとも自然に寄り添えるのです。
「だら燗」という釧路だけの燗酒文化
実は釧路は「炉端焼き発祥の地」とも言われていて、こうした食風景の中に地域のアイデンティティが色濃く現れています。炭火で新鮮な魚介を焼きながら一杯やる──そんな食文化の中で、ユニークな燗酒スタイルが育ちました。それが「だら燗」と呼ばれる燗酒です。
陶製の壺に福司を入れ、囲炉裏の炭火のそばでじっくりと温め、竹の柄杓で湯呑みにすくって注ぐ。そんな、風情あるスタイルで提供されるだら燗は、人肌燗(約35〜40℃)くらいの温度帯の、まろやかで優しい味わい。さらに「だら燗」は炉端ごとに微妙に異なります。炭火との距離や器の素材によって、酒の味が変わる。つまり、“ライブ感のある燗酒”とも言えます。

だら燗
季節ごとの味覚と、地酒の楽しみ方
釧路の魅力は、季節の味わいとともに地酒を楽しめることにもあります。たとえば、冬には醪を荒く濾したにごり酒「活性酒 純生」と、真だち(鱈の白子)の天ぷら。新年を迎えてから春にかけては、フレッシュなしぼりたて生酒とともに味わうクジラや毛ガニ。いずれも、釧路ならではの贅沢なペアリングです。
また、釧路の名店「つぶ焼かど屋」では、名物のつぶ焼と真っ黒なラーメン、そして福司の一合瓶が定番の組み合わせ。さらに、「SL冬の湿原号」や「くしろ湿原ノロッコ号」といった観光列車の中では、ダルマストーブでスルメを炙りながら、福司を味わうという、寒冷地ならではの体験もできます。
釧路の日常に、福司がある
“選ぶ”のではなく、そこに“ある”お酒。

「釧路に来ると福司って、どこにでもありますね」と言われることがよくあります。これは道外のお客様だけでなく、道内の他地域から訪れた方にもよく聞く声です。けれど、私たち地元の人間にとっては、それが少し不思議に感じられます。というのも、福司はあまりにも“当たり前”の存在だからです。
実際、ラーメン屋さんにも福司。ザンギの名店にも福司。居酒屋のメニューには“福司”の文字が並び、スーパーやコンビニ、ドラッグストアにも季節の限定酒が並びます。どこに行っても、さりげなくそこにある。その風景は、外から訪れた方にとっては少し不思議で、かえって印象的に映るようです。そうした声を聞くたびに、私たち自身もこのまちの風景をあらためて見つめ直すきっかけをもらっているように感じます。
地域の声と地酒らしさ
福司は、地元の方にとって“こだわって選ぶお酒”というより、“気がつけばそばにあるお酒”なのかもしれません。年末年始の食卓や地域のイベント、ちょっとした景品や手土産として。お祝いの席では「とりあえず福司」、日常の手土産には「やっぱり福司」といった具合に、特別な理由がなくても自然と選ばれている。そんな光景をよく目にします。
もちろん、それは私たちが意図して仕掛けてきたものではありません。地元の皆さまが、長い時間をかけて“釧路のお酒”として育ててくださった結果だと思っています。地元で開催される日本酒イベントでも、私たちのブースに長い行列ができるわけではありません。けれど、「いつも飲んでるよ」「この前の限定酒、美味しかった」と、親しみのある言葉をかけてくださる方がたくさんいらっしゃいます。まるで親戚に声をかけられるような、そんな距離感がとてもありがたく、嬉しいのです。
昔から地元で親しまれてきた“だら燗”や、地元新聞に掲載されている「晩酌の一杯」の広告も、福司がこの地域に根づいていることの証だと感じます。だからこそ、私たちは“地酒”という原点を忘れずにいたい。福司は釧路という土地で生まれ、このまちの空気や人々の暮らしとともに育ってきた酒です。これからも日々の生活にそっと寄り添いながら、静かにそこにある存在でありたいと考えています。
この地元での福司の在り方は、言葉だけでは伝えきれないものがあります。だからこそ、実際にこの地域に足を運び、肌で感じてもらいたいと思っています。私たち製造部でもお客様が来ると一緒にこの世界観の中で福司を飲み、造りの話をします。私たちのとっても力を発揮できる最高のフィールドです(笑)
変わらないものと、変えていくこと
「地酒」であることに、誇りと可能性を。

次の100年を見据えたブランド「五色彩雲」
「福司って、そこにあるもの」
そう言ってもらえることは、私たちにとって何よりの誇りであり、酒造りの根源です。釧路で生まれ、育てられ、日常にそっと溶け込んできた地酒・福司。しかし、私たちはただ守るだけの蔵ではありません。このまちで培った「福司らしさ」を軸に、次の100年を見据えた挑戦も始めています。
それは、気候変動によって変わりゆく北海道の食文化に寄り添う新しい味わいであったり、意外な素材との出会いから生まれる新たな日本酒の表現であったり、これまでにない飲み方の提案であったり。“地酒”の可能性を、もっと自由に、もっと楽しく広げていきたいと考えています。
なぜなら、地元の人たちの日常にある酒だからこそ、変化する時代に合わせて進化していく必要がある。守るべき原点があるからこそ、変えることも恐れない。それが、これからの福司の姿です。そしてそれを造る人を育て、受け継いでいかなければ、地酒として残り続けることが難しいと考えているからです。
その土地で、私たちにしかできない酒づくりが、きっとあるはず。これからも「酒蔵だより」を通して日本の右端から、“福司のこれから”を少しずつお届けしていきたいと思います。どんな想いで酒を造っているのか。どんな香りや味わいを目指しているのか。そして、新しい挑戦の裏側には、どんな物語があるのか──そして私たちが思い描く、今の時代の地酒の在り方など
「飲んでみたい」「もっと知りたい」
そう思っていただけるような地酒であり続けるために、私たちはこれからも、釧路、そして北海道という可能性あふれる大地と向き合いながら、酒づくりを続けていきます。
次回もどうぞ、お楽しみに。
【酒蔵だより:福司酒造】
- ・2025年5月:これがチーム福司!釧路で日本酒を造る人々を紹介
- ・2025年6月:北海道の“右側”にだけある風景。釧路と福司の話