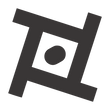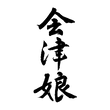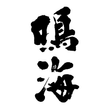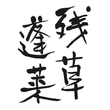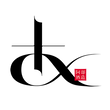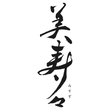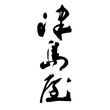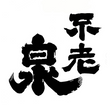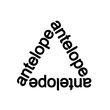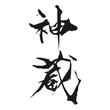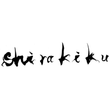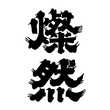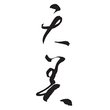国内外でその高い技術が評価されている「山丹正宗」醸造元の八木酒造部(愛媛県)。5月に結果が発表された令和6酒造年度全国新酒鑑評会にて、2年連続金賞を受賞しました。今回の酒蔵だよりでは、結果を出すための取り組みやこれからの酒造りについて、八木酒造部8代目蔵元の八木伸樹さんに綴っていただきました。
全国新酒鑑評会で2年連続金賞を受賞

「山丹正宗」醸造元の八木酒造部は、令和6酒造年度の全国新酒鑑評会にて、2年連続24回目の金賞を受賞しました。19年前に私が蔵に戻ってからは14回目の金賞受賞で、今年は愛媛県で唯一の金賞受賞蔵となりました。
昨今、世界中でたくさんのお酒のコンクールが開催されていますが、日本酒においては全国新酒鑑評会が最も歴史があり、参加酒蔵数も最大となります。主催は酒類総合研究所ですが、もともとは国税庁が主導していた公的なコンクールです。
特徴的なのは、料理との相性や味の個性を競うのではなく、いかにクセの無いきれいなお酒を造れるかで杜氏の技術を競う競技であるという点です。そのため、出品酒のほとんどは最もきれいなお酒が造りやすい山田錦の大吟醸であり、地域性や蔵の特徴などはほぼ感じられません。ですが、全国の杜氏が心血を注いで造ったお酒なので、通常の市販酒にはない煌めくような香りや、唸りたくなるような奥深い旨味に出会うことができます。
2024年の金賞受賞に至る取組み

クセの無いお酒を造ろうと思うと、純米大吟醸よりも醸造アルコールを添加した大吟醸の方が有利になります。なぜかというと、
①醸造アルコールにより吟醸のフルーティな香りが揮発して感じやすくなる
②雑味の原因となる成分が無味無臭の醸造アルコールで希釈される
ということが挙げられます。そのため、数年前までは毎回、金賞受賞酒の90%以上がアルコール添加した大吟醸でした。
一方で、アルコール添加したお酒の消費者離れが進んでおり、出品酒を作っても(あるいは金賞を受賞しても)大吟醸が売れないという状況に多くの蔵元が悩まされていました。当社も例外ではなく、このままだと大吟醸の売上が落ちて仕込みの量が減り、小仕込みとなって品質が安定しなくなることで売り上げが落ちるという悪循環に陥るのが目に見えていました。
そこで、石田杜氏と相談し、2023年から「金賞を取ることよりも売れることを優先しよう」と、出品酒を純米大吟醸に切り替え、「いつかまた金賞が取れるように」と純米大吟醸での技術を磨くことに専念しました。
すると、最初の2023年に「入賞」、2024年には「金賞」と、予想外でしたがいきなり結果がでました。勝因としては、
①徹底した品質管理、衛生管理により、オフフレーバーを押さえることができた
②全国新酒鑑評会の審査基準が純米大吟醸を拾う方向で緩やかに変更された
という2点が考えられます。
特に審査基準については、以前は酸度が1.0に近いお酒が評価され、どうしても酸度が1.2~1.4程出る純米大吟醸は不利だったのですが、雑味ではない酸は減点されなくなったことが大きいと感じています。
2025年の酒造りで目指したこと

2024年のお酒がほぼ理想的な出来栄えだったので、2025年の基本方針は「2024年の踏襲」でした。しかし、昨今の猛暑による高温障害で原料米が年々溶けにくくなってきており、例年以上にお米を溶かすための努力は必要でした。
具体的には、いかに強い麹を造るかという点で、麹菌の種類の見直しから入りました。結果的に思ったほど強い麹にはならなかったのですが、酒質としてはほぼ狙い通りのお酒ができました。
金賞受賞酒は、「山丹正宗 雫取り純米大吟醸酒」として発売しております。
連続受賞後の酒造り
全国新酒鑑評会は、あくまで杜氏の技術の研鑽の場であり、その技術を生かして造る市販酒こそが、自分たちが最も努力すべき世界だと思っています。そういった意味では、現在の当社の取り組みとして、
①今後ますます溶けにくくなるであろう酒米で、いかにきれいなお酒を造り続けていくか
②水酛やオーガニックなど、日本酒の新しい価値観をいかに生み出していくか
というところに注力しており、それを実現するために出品酒で腕を磨く、といったところでしょうか。
今年の金賞受賞酒である「山丹正宗 雫取り純米大吟醸」は、石田杜氏が精魂込めて醸した力作です。とにかくクセがないので、お酒好きはもちろん、日本酒を飲み慣れていないビギナーの方にもおすすめです。料理をつつきながら、だらだら飲むというよりは、最初に佃煮や夏野菜など、軽いアテでお楽しみください。
【酒蔵だより:八木酒造部】
- 2023年夏:「水もと仕込みに初挑戦した「山丹正宗 華帯」」
- 2023年秋:「水酛造り第2弾「山丹正宗 MINAMOTO」について」
- 2025年春:「蔵の柱。定番酒「山丹正宗 純米酒 松山三井」ってどんなお酒?」
- 2025年夏:「連続金賞受賞の裏にあった決断とこれからの酒造り」