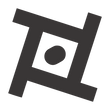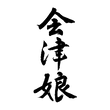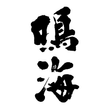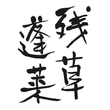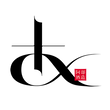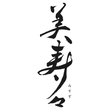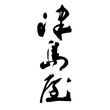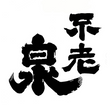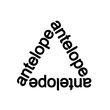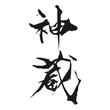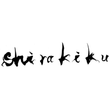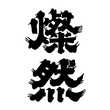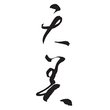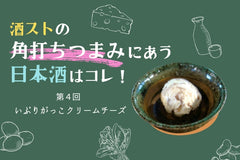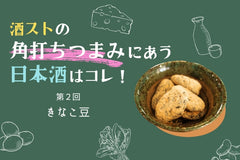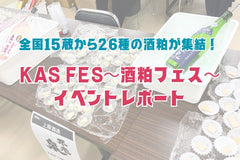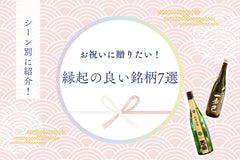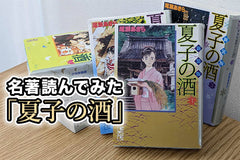燗酒に料理を合わせるなら、おでんなどの伝統的な和食。フレンチにお酒を合わせるなら、ワイン。多くの人が持つであろう、そんなステレオタイプなイメージを完全に覆すイベントが9月に開催されました。
この会を仕掛けたのは、SAKE Street Webメディアの人気ライターでもあり、酒販店員・SSI研究室専属テイスターでもある山本聖治氏と、創造的なフレンチ技法を生かした五反田の人気店「Burger&Bistro Occi」シェフの山口弘氏。
日本酒ペアリング研究家である私・酒井が、両者のタッグによるイベントに潜入し、フレンチ×燗酒の極意を学んできました。
なぜ燗酒なのか?
そもそも、なぜ「フレンチに燗酒」なのか。イベント開始前に山本さんに尋ねたところ、次のように語ってくれました。
「シェフ・山口さんの提供する料理がフレンチである以上、お客様がワインと比較してしまうことは避けられません。また、山口さんには以前から、私の燗酒への向き合い方を評価いただいていることが、今回の会のきっかけになっていると感じています。
ならばワインにはできない、日本酒だからこそできる表現、そして評価いただいている技術である『燗』にこだわることが、自分が呼ばれた意味がある提供の仕方になると考えました。」

会場にはすでに、山本さんが今回の会に向けてセレクトした10種類ほどのお酒が並んでいます。イベントの開始時間が迫り、どんな料理に、どのお酒の燗酒が選ばれるのか、ワクワクが止まりません!
ここからは、会での提供の流れに沿って、料理とお酒の味わい、燗酒にしたときのペアリングのポイントを紹介していきます。
①シャインマスカットと山羊リコッタチーズとナッツの白和え

最初に提供されたのは、「シャインマスカットと山羊リコッタチーズとナッツの白和え」(右)と「牛と牛蒡の煮凝りテリーヌ」(左)の二種盛り合わせ。
まずは白和えから行きましょう。和え衣に山羊乳独特の癖はほとんどなく、やや強めの塩気とうま味の濃さでなかなかのインパクト。ここに瑞々しいシャインマスカットが加わることで、和え衣の強さが緩和されてバランスが取れる設計になっています。さらに砕いたナッツがアクセントとしていい仕事をしています。
ここに合わせるお酒は「醸し人九平次 うすにごり生 2023」。年に一度しか販売されない限定品で、さらに山本さんが半年ほど生熟成したもの。冷酒で飲ませてもらいましたが、スムーズで流麗な中にふくよかさも内包しており、全く悪いところが見つからない。さすがに絶品ですね。

これを燗にすると、ほんのりした生熟成の香味がまとまりを得て、ナッツの風味とリンクします。うすにごりの柔らかさも白和えのとろりとしたテクスチャーと合致して、いきなりハイレベル!
②牛と牛蒡の煮凝りテリーヌ
やや甘めの味付けで、ゴボウの土臭さをしっかり生かした一品。
ここには「FUSION 大盃 丹波ワイン樽熟成」を合わせます。口当たりはまろやかながら、酒質としてはパンチ強めで、そこにワイン樽由来のバニラ香やスモーキーな香ばしさが加わるため、単品だとややクセの強さも感じるお酒です。

これを温めることで、バラつきのあった香りやボディ感が一つにまとまってきます。ゴボウと牛というパワフルな食材と、お酒のパワーが拮抗することでバランスの取れたペアリングが実現。さらにスモーキーな香りがゴボウの土臭さとぴったりマッチ。樽酒とゴボウの相性はテッパンですね。
③酒粕入りクラッカーと酒粕バターソース
ただのクラッカーでは日本酒と合わせることが難しいのですが、こちらはクラッカーの生地とバターに酒粕を練り込むことで、極限まで日本酒との相性を高めています。

ここには「無窮天穏 斎香 原酒」を合わせます。天穏のお酒らしい清らかさのなかに、米の旨味をはじめとして、味わいの要素の数が多いお酒です。

常温ではアルコール感をやや強めに感じましたが、お燗にすることで全体がふくよかにまとまります。さらに生酛らしい米の味わいが増して、バターの脂っぽさにベストマッチ。お酒のもつ糠の風味とクラッカーに練り込まれた酒粕の風味が融合していきます。
④バゲットと三右衛門豚のジャンボンブランサンド
個人的に、この日のハイライトとなったのがこちらのペアリング。一見地味ですが、非常に画期的な組み合わせでした。これまで常々、パンと日本酒は相性が悪いと感じていました。それがまさか今日、ガラっと覆されるとは!
市販のパンでは合わせづらかったと思いますが、今回はこの日のためのハンドメイド。バゲットに使う砂糖を酒粕に置き換えるという工夫が施されていました。
山口さん曰く「パンから日本酒と合わない要素を排除していった」とのこと。イースト臭が大幅に低減していることで、違和感なくペアリングできるんですね。
合わせたお酒は「会津娘 純米酒 一乃正宗」。

戦前戦後の酒造りで使用した道具を用いて仕込んだ古式の生酛、というとクラシカルな味なのかなと想像しがちですが、これはむしろモダン。生酛ならではのきれいな酸が特徴的で、燗にすることで米のうま味も前に出てきます。
これまた面白いのはジャンボンブラン(豚肩ロースのハム)で、脂が多めで塩気はかなり抑えてあります。それによって、お酒の味を変調させずに穏やかに同調する上品なペアリングが実現されていました。
⑤白身魚、カニのフィッシュクラブバーガー

シェフの山口さんが「今、最も美味いと思っているバーガー」とのこと。その言葉のとおり絶品で、蟹と白身魚の旨味に、ほのかな酸味のソースが加わり、強めに焼いた香ばしいバンズとクリスピーな具材が一体となった食感を楽しめます。100個でも食べられそうな美味しさです!
これに合わせるお酒は「風の森 ALPHA5」と「伊根満開」をブレンドし、温めたもの。

「風の森 ALPHA5」は燗酒用として造られた商品で、同銘柄のほかのラインナップよりも落ち着いた味わいが特徴です。そこに古代米で醸した、ベリー系の熟した果実を思わせる酸味が特徴の「伊根満開」で酸を加えて、ソースに合うようチューニング。蟹のしっかりとしたうま味に、日本酒のうま味が重なって増幅されます。
ちなみに、こちらのバーガーのバンズは先ほどのように酒粕等は加えられておらず、通常の製法のもの。このため、バンズ単体ではどうしても日本酒と合わせづらいのですが、それでも良いペアリングになるのは具材の存在感が大きいからですね。
シーフード特有の風味が日本酒を引き寄せるため、他の部分で多少のミスマッチがあっても全体としてはバランスの取れたペアリングになるのです。
⑥揚げ出し豆腐 ポルチーニのクリームソース

非常に濃厚なポルチーニのソースを一口含むと、キノコの独特な風味が鼻腔を抜けていきます。経験したことのない、特徴的な味わいです。これを味の淡い揚げ出し豆腐と一緒に食すことで、濃厚さと軽やかさがコントラストを生みつつ、両者の柔らかいテクスチャーがシンクロすることで料理にリズムを与えています。
お酒は今回もブレンドで、「瑞冠 熟成純米原酒」と「久保田 萬寿」の組み合わせ。

瑞冠は10年の長期熟成酒なので、それなりの重さと古酒独特の香味があり、それがポルチーニの土っぽさとよく同調します。ただ、このままでは料理に対して少し重すぎるんですよね。そこで軽快な久保田を加えることで濃度を調整しています。
山本さんが料理の特徴を的確に捉え、お酒の選択や温度だけでなく細やかな調整を加えることで、繊細なバランスの料理にしっかり対応できていることが分かります。
⑦あん肝のプリン

まず蓋を開けると、真っ黒いビジュアルに度肝を抜かれます。蒸したあん肝の上に、たまり醤油とカラメル、赤ワインなどで仕上げた、甘苦いソースがかかっているのです。これはすんごい……濃厚旨味爆弾。
このパワーにはパワーで対抗するしかないでしょう。というわけでチョイスされたのは「不動 貴醸酒:RE」。生酒のまま4年間熟成したお酒を、さらに貴醸酒にするというマニア垂涎の製法でつくられたお酒です。

これはお酒の強度も甘味もうま味も、全てにおいてあん肝のプリンと完全同調。「押して押して押しまくる!」というペアリングですね。冷酒だと味が締まってしまうので、こうは行かなかったでしょう。
⑧若鶏トマトクリームのビリヤニ風

締めの料理は、まさかのビリヤニ!トマトクリームと和えてあるのでリゾットのような趣があります。スパイス感は控えめなので、日本酒とも合わせやすい味わいです。
ここには「真上 特別純米 生原酒」を。酒ストでも人気の、甘酸っぱくジューシーなお酒です。

比較的抑えた味わいのビリヤニに、お酒の酸味と旨味が加わり、全体の風味をさらに押し上げる面白さがありました。最後の組み合わせで、同調というよりもワイン的なペアリングの要素を感じます。お燗にすることでお米の風味が増し、ビリヤニのお米と調和する一体感も楽しめました。
まとめ
全8品のペアリングを存分に堪能させていただきました。今回の料理はあくまでフレンチをベースにしながらも和の食材を使用したり、日本酒に寄せる工夫をしたりと、どれも単なるフレンチの枠を超えた素晴らしい創作料理になっていました。
ペアリングにおいて特に印象に残ったのは、やはりバゲット。日本酒とパンはずっと鬼門だと思っていただけに、酒粕を使ったパン側からのアプローチは目から鱗でした。
さらにすごいのが、これらのペアリングは事前に練られていたわけではなく、ほぼぶっつけ本番のアドリブ、とのこと。
山本さんはある程度料理の当たりをつけて、それに対応できるよう10本強の日本酒を選んでおく。一方で山口さんもある程度日本酒に寄せた工夫をする。この両者が重なることで、これだけの創造的かつ楽しいペアリングが作り上げられるんですね。
飲食店と酒販店、と異なる立場ですが、普段から交流のある2人だからこそできるワザだと感じました。いやはや、感服しました。同業の人間として、その難易度がわかるだけになおさら。
ペアリング研究家としても大変勉強になる機会だったので、今後お二人が開催する会もとても楽しみにしています!